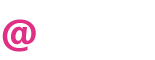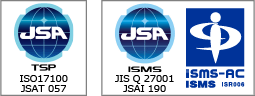CQ Business®による真のグローバル力とは?異文化理解が国際展開の鍵
株式会社アットグローバルは翻訳会社であることに誇りを持ちながら、その枠を超えた価値を提供しています。
私たちは、CQ(Cultural Intelligence Quotient)の考え方を取り入れ、言語を超えて文化や背景への深い理解を大切にした翻訳を心がけています。このアプローチにより、単なる言葉の変換ではなく、読み手の心に響き、共感を生む翻訳をご提供しています。
さらに、私たちはセミナーを通じてCQの重要性をクライアントにお伝えし、異文化コミュニケーションの本質を深く理解していただけるよう努めています。CQの概念を現場に浸透させることにより、企業の国際展開や異文化市場での成功の鍵となることを実感していただけるはずです。
また留学予定者向けのプログラムでは、異文化という環境を最大限生かして成長につなげるための準備をお手伝いすることで、若い時から真のグローバル力を身に着けるよう助けています。
本記事では、弊社が実施しているCQセミナーの概要とその魅力をお伝えするため、講師を務める蔭山へのインタビュー内容をお届けします。セミナーの特徴や意義について深く掘り下げた内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
CQは、文化の違いを体系的に表現する尺度

―― 今回は、アットグローバルCQチームのメンバーである蔭山さんにインタビューして、CQの魅力についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
蔭山)よろしくお願いいたします。
―― さっそくですが、蔭山さんのこれまでの背景を教えていただけますか?
蔭山)はい。父親が転勤族ということもあり、子どもの頃から中東、大韓民国に住んだり、欧州やアジアの国々を訪ねたりする機会がありました。
社会人になってからアメリカ留学とインターンシップを経験後、仕事で上海に住み、コロナが始まってから帰国しました。合計22年ほどを海外で過ごしてきたことになります。
―― 子供のころから、さまざまな文化の中で生活してこられたわけですね。どのようにCQに興味を持たれるようになったのでしょうか?
蔭山)きっかけは文化の違いに興味を持つようになったことです。アメリカ留学時には、アメリカ人対日本人で比較する傾向があり、この二国は文化的に対極にあるように感じました。
でもその後、上海に住んだ時に職場で多くのヨーロッパ人と接するうちに、時間の感覚やコミュニケーションスタイルの面などで、ヨーロッパとアメリカの文化間にも大きな差異があることを知り、むしろ日本とアメリカのほうが感覚が近い場面さえあることを意識するようになりました。
もちろん同じアジアの国である中国や韓国で生活した経験の中でも、アジアでひとくくりにできない文化の違いを感じていました。
それで世界は、日本とアメリカというような二元論的な捉え方からではなく、さまざまな文化の似ている部分や異なる部分の複雑な絡み合いとして捉えるべきことに気づいたものの、その時の自分には言語化できないものであると感じていました。
というのも文化の違いについて他の人に説明する際、エピソードは話すことはできるものの、体系的に説明できなかったからです。それでぜひ、何か見える指標や知識としてまとめたい、と感じていた時にCQの研究に出会いました。
現在もCQから様々なことを学んでいますが、もっと早く知っていたらこれまでの生活ももっと楽しめたのではないか、と思います。CQの知識があれば、ビジネスだけでなく、生活の中でも多くのメリットがあります。そして外国人と接する機会が少ない人であっても役に立つと感じています。
CQとは?

―― なるほど。いくつもの国に住んで来られた蔭山さんだからこそ、気づきがあったわけですね。ここまでCQ、CQと言ってきましたが、CQを定義から説明していただけますか?
蔭山)CQはCultural Intelligence Quotientの略で、「文化の知能指数」と訳されることが多いですが、簡単にいうと異文化対応力のことです。その対応力は、異なる文化や価値観に対応するためのマインドセットと知識に基づくもので、両方同時に持ち合わせている必要があります。どちらか一つだけでは目的を果たすことができません。
そして座学としてCQについてのマインドセットと知識を身に着けるのみならず、実際の場面に当てはめて応用していくことが必要になります。セミナーではシナリオ・経験談をお話して、スキルを強調したり実際にどう行動すると良いのかを練習したりしてCQの実際の活用方法を紹介しています。
マインドセットと知識
―― もう少し具体的に教えてもらえますか?
蔭山)セミナーでは、よくこういうイメージをお伝えしています。例えば、自分の生まれ育った地域の文化を、島に例えたとします。そして別の文化を少し離れた別の島に例えてみます。水面上に見える文化は大きく異なっているように見えるかもしれません。水面下には、文化の基盤となる歴史的背景、価値観の違いがあります。
でも、少し俯瞰してみると島として見える部分はほんの一部分で、水面下のもっと深い部分を見ると私の島と隣の島は実は繋がっています。
人間としての共通部分は実は同じであるものの、歴史背景や環境ゆえに異なる文化が存在するようになったにすぎず、もし自分が隣の島で生まれ育っていたら、そちらの文化に影響を受けた考え方や価値観を持っただろう、と想像できます。
そのように自分と他の人の共通部分と異なる部分を理解できれば、相手を尊重し、今回は相手のやり方に寄せてみようかな、あるいは今回はこちらのやり方でやりませんか、と提案してみようかな、と対応を決めることができるようになります。
―― なるほど。これがマインドセットなわけですね。知識の部分はどうでしょうか?具体例がありますか?
蔭山)例えば、東南アジアの多くの地域では、残業をしない働き方が主流です。定時で家に帰り、家族と一緒に時間を過ごすことで家族を大切にする文化です。
一方、すぐお隣のインドは、特に管理職やIT業界などの世界では競争の激しい社会であるため残業をいとわない人も多く、それが社会的にも受け入れられています。でも彼らが残業をする理由は、自分が一生懸命働いて家族に経済的な安定性をもたらしたい、という動機から来ています。
つまりこちらも家族を大切にしているからなんです。このようにどちらの文化も家族思いなのですが、歴史的・社会的背景が異なるため、違う形で表現されている、ということになります。
CQの活用方法

―― 興味深いですね。ではこれらのマインドセットと知識をどのように活用すればいいのでしょうか?
蔭山)よくありがちなケースですが、たとえば日本企業が東南アジアに工場を建てました。納期が迫っているので現地の従業員に残業をしてほしいと頼みますが断られてしまいます。
一般的に納期が家族よりも優先される文化で育った現地の日本人マネージャーには理解ができません。残業を強要すると従業員が怒ってやめてしまうということが起きます。
お互いに文化的背景を理解しようとせず、自分の価値観を相手に押し付けてしまうとこうなってしまいます。
もちろんこの点で、ステレオタイプにならないように注意をする必要があります。同じ文化の中で育っても考え方・経歴が異なるので、個人レベルで異なることがあります。東南アジアのケースでも喜んで残業する人もいるでしょう。
ですからそこは東南アジアだからと一まとめに括ってしまうのではなく、個性、遺伝子、教育背景が異なるゆえに異なった行動をする人もいることを踏まえたうえで、その国・地域の傾向を理解しておくこと、文化の影響を過大・過小評価しないことが重要です。
―― 非常に分かりやすく、バランスの取れた見方ですね。でも今の東南アジアのケースだとどこで調整を図ればよいのでしょうか?
セミナーの内容になってしまうので、どこまでこのインタビュー記事に書けるか分かりませんが(笑)、少しご紹介しますね。
大切なのは、最初のチームビルディングの時に、しっかりとコミュニケーションを取ることです。業務の前に日本企業側と現地の従業員側がお互いを理解する時間を取り、文化的なすり合わせをすることで摩擦を避けることができます。一見、時間の浪費のように思うかもしれませんが、結局は時間短縮、スムーズな業務の遂行につながります。
ただし、チームビルディングではなんとなくダラダラ話すのではなく、目的を持って話し合う必要があります。例えば、お互いにこんな風に質問し、相手の話をよく理解するようにします。
(質問例)
- 私の文化では、人が発言している時に、質問するのは失礼と感じますが、あなたの文化ではどうですか?このチームではどうしましょうか?
- 納期という言葉はあなたにとって何を意味しますか?目標ですか、それとも絶対的なものですか?
などです。適切なCQの知識とスキルを発揮しながら話し合うことで、相手を理解でき、その考えを尊重できます。そうすれば、普段は残業をできるだけお願いしないようにし、本当に困った時だけ助けてくれるようにお互いが歩み寄る方法を見つけることができるでしょう。
CQの活用範囲は無限

―― CQの価値の片鱗が見えてきました。お互いを理解できる環境が整うことで、その後の仕事もスムーズにできそうですね。ところで蔭山さんは、冒頭で「もっと早くCQを知っていれば、これまでの生活ももっと楽しめたのではないか」とおっしゃっていましたよね。それはどうしてですか?
蔭山)アットグローバルとしては、CQを主にビジネスで活用する方法をセミナーでお伝えしていますが、実際には、CQは生活のあらゆる面で役に立ちます。
CQを使いこなすことができれば、トラブルを上手に乗り越えて、多様な環境を楽しんだりアドバンテージを引き出したりできます。CQが低ければ、ひたすらストレスを受けて、仕事や家族のメンバーの能力を発揮できなくなります。CQがあれば、1+1=3になりますが、CQがなければ1+1=0になるイメージです。
例えば、日本の中でも大阪と京都では全く文化が異なりますよね。大阪人は初対面なのに他人の年齢をすぐに聞いてくることがありますが、京都人にはその感覚は考えられないことです。でもそういう文化で育った人だと分かっていれば、驚くこともありませんし、異文化を楽しむことさえできます。
またゆとり世代、Z世代などとのジェネレーションギャップが取りざたされることがありますが、親子や上司部下という立場の違いや年代の違いというよりは、育った時代背景が異なることが主な原因である場合があります。
こういうCQのマインドセットと知識、そして実践するスキルを身に付ければ、仕事でもプライベートでも、対人関係でのストレスは激減します。違いを楽しむ余裕が生まれるんです。
アットグローバルのCQセミナー内容

―― 素晴らしいですね。CQの概念を適用できる範囲は無限ということですね。ここまでこの記事を読んでくださった方なら、ぜひCQのセミナーに参加してみたいと思っておられると思うのですが、アットグローバルではどんなセミナーを開催しているんでしょうか?
蔭山)現在アットグローバルでは、対面/オンラインの形式でセミナーを実施しています。全般的な内容を扱うCQベーシック編から海外ビジネスでよく遭遇するシチュエーションを扱ったマネージメント編や交渉編など複数のコースをご用意しています。
セミナーの対象は、大きく分けると以下の4つになります。
- 留学予定者
- 社員全般
- 経営者
- 日本で働く外国人
内容は基本となるものがありますが、一律のものを提供しているわけではありません。前もってヒアリングをした上で、そのクライアントのニーズを満たせる内容に寄せて準備をします。
「なぜ異文化をもっと理解したいのか?」「何のためにCQを高めるのか?」を明確にさせ、クライアントのゴールを達成できるよう、セミナー内容をカスタマイズします。留学予定者か社会人かでも内容が違いますし、企業向けのものでも一律ではなく、それぞれのグローバル戦略に沿ったカリキュラムを組みます。
―― 基本部分は同じですが、それぞれの目的に合わせたセミナーを準備するということですね。ぜひともCQを世界に広めてほしいですね。ところで、最近行ったセミナーで反響の良かったものはありますか?
セミナーの反響について
蔭山)そうですね、例えば先日、ベトナム、インド、中国などで海外展開をしておられる企業を対象にCQセミナーを実施させていただきました。
受講者は、国内で働かれている若手の社員さんが中心でした。セミナーを受けて、社内の外国人と働く際にCQのスキルを適用することでスムーズなコミュニケーションを図れると喜んでくださいました。
またCQの説明には文化に関する種々の指標が取り入れられています。例えば、「時間に対する態度」「直接的・間接的なコミュニケーション」「権威に対する態度」などたくさんの項目があり、それぞれの項目で、ある国は重要視するが、別の国ではそれほど重要視されない、というように文化的特徴が国地域別に数値化、見える化する研究が行われています。
指標をもとに考えることで、その国の人と今まで接したことがなくても、ある程度その国の文化を推し量ることができます。この点について話した時、驚きの声が上がり、興味深かったですね。
もう一つ、印象的だったのは、謝罪に関する点を取り上げる時です。多くの会社では、外国人社員が謝らないことに日本人社員がストレスを感じる状況があるようですが、実は、相手に謝罪を期待する面で、日本の文化には特殊な面があります。
「世界の多くの国で日本人は相手の国の人が謝らないとストレスをためてしまうことが多いのですが、実は日本の文化の方が珍しいのだということを知るだけで、いら立ちが軽減する部分もあるのではないですか?」と尋ねると、頷かれる参加者の方が多いです。
―― 日本は謝罪の文化なんですね、知りませんでした。申し訳ありません。(笑)
受講した人の感想
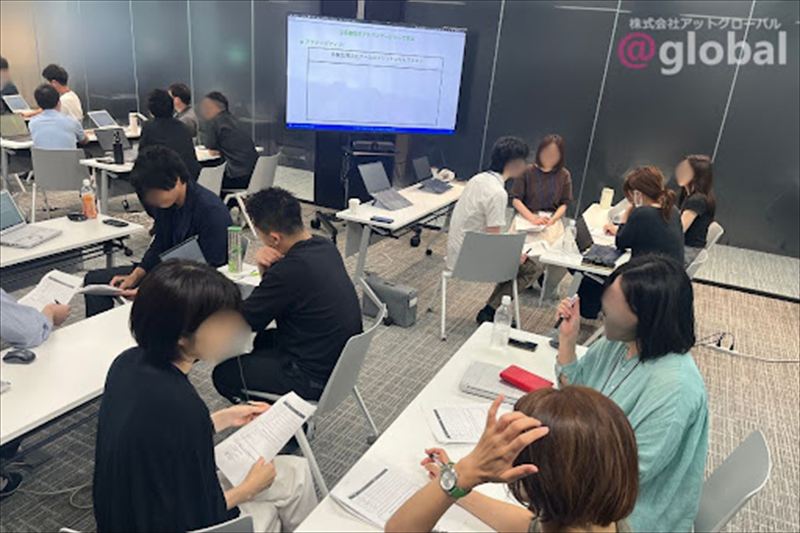
―― このセミナーの後に実施したアンケートでリアルにお答えいただいた感想をいくつかご紹介したいと思います。
Aさんの感想)
かなり有意義な内容だと思った。なんとなく、自国と他国でのカルチャーの違いがある事はわかっていたが、国によって全然異なる事を改めて理解できた。”外国人”を一緒くたにするのではなく、相手のルーツを正しく理解する事の重要性を認識できた。
Bさんの感想)
異文化に触れた際何で分かってくれないんだ、と思う場面があっても、根底にあるものが異なるのかもしれない、と考えられるようになることが、自身の許容範囲や対応の幅が広がることにつながると思った。
―― 講師を務めた蔭山さんとしては、このアンケート結果をどのように感じられますか?
蔭山)そうですね。基本、内容に満足してくださったようで、うれしいです。セミナーは、限られた時間で特にその企業様の社員さんのニーズにあったコンテンツを提供する必要があり、毎回大きなプレッシャーを感じますが、毎回、満足したという感想が多いので、また次回も頑張ろうという励みになっています。
ありがたいことにCQセミナーをとても気に入ってくださり、海外赴任する社員向けに継続的にご依頼してくださっているクライアントもあります。今後も、セミナーで直接皆さんとお話しする機会を大切にしていきたいです。
CQセミナーの申込みの流れについて
―― 私もとても勉強になりました。さて、もしアットグローバルの提供するこのCQセミナーに関心がある方は、どのように問い合わせ、あるいは申し込みを行えばいいのでしょうか?
蔭山)はい、まずは問い合わせフォームからご連絡ください。
ご連絡いただいたあとは、直接CQチームがヒアリングを行わせていただきます。まずは、CQに関するアットグローバルの取り組みについてご説明いたします。そして企業様のニーズのヒアリング、そしてヒアリングに基づいたセミナー内容の打ち合わせ、となります。その後弊社にてサンプルスライドを作成させていただき、時間・内容・会場を確認した後、ご契約という流れになります。
―― なるほどです。契約は、ご提供する内容に納得いただいてからということになりますね。安心してまずは問い合わせをしていただければと思います。
蔭山さん、本日はインタビューにご協力いただき、ありがとうございました。私たち自身もグローバル企業で働く一員としてCQを磨いていきたいですね。そしてこれからも、一人でも多くの方がCQのメリットを実感できるよう頑張ってください!